Diary03
いちはやき遅れ
四年制大学 卒業見込み/文学
エントリーシート提出
2024年3月12日(火)
「本は、ひとつの宇宙だと教えてくれたのが、新潮文庫だった。この宇宙は、読者がいるかぎり、それがどれだけ小さく、また暗く儚いものであっても、無限である」。エントリーシートの冒頭にそう書きつけたわたしは、しかし書くことで、自分自身にそう思い込ませようともしていた。書物は人を幸福にしない場合も多いし、たいていの場合、現実に対してどうしようもなく無力だ。それでもフィクションをつくる仕事をしたいのはなぜなのか。「本が好き」、という所与のものだと思いつづけていた自分の感情を疑いつつ空欄を埋めていたら、気がつくと提出の締切を過ぎたも同然の時刻になっていた。
この日に読んだのはフローベール『ボヴァリー夫人』とマルコ・バルツァーノ『この村にとどまる』。いきおいでESにも盛り込む。
適性検査・知能テスト(Web実施)
2024年3月19日(火)~28日(木)
四つ上の姉が使っていたSPIの問題集を引っ張り出して、眺めるだけ眺めてから臨む。とくに手ごたえはなかったが、落ちるとしたら締切前にあわてて書いた作文の汚い字のせいだろう、と達観(?)していた。一月末に就活をはじめ、この時点で受験した企業が四社。SPIを受けたのが二回目だったので、WEBテストに対する経験値はない。遅れてきた就活生だという自覚があった。
この日に読んでいたのは平松洋子氏の「銀の皿 新潮社社食の半世紀」
(https://www.shinchosha.co.jp/nami/tachiyomi/20170727_2.html )。働く自分より、毎日社食を食べる自分の方がイメージできた。
一次面接
2024年4月17日(水)
「人生ではじめて触れた“むずかしい”本は?」と訊かれて、ダンテの『神曲』と答える向こう見ずな受験生ことわたし。実は中学生のころ、授業中に隠れて読んでいた『神曲』を没収されて、あだ名が一時期“かみきょく”になったことがある。そんなことはどうでもいいが、面接の待ち時間のあいだはどこか場違いな感じもしていたのに、いざはじまると自然体の自分が引き出されていって、あっという間に終わってしまう。面接をしてくださった社員の方々はとても聞き上手で、次回以降の面接に役立つアドバイスもしてくれた。ただ、圧倒的に短い時間の面接なので、自分の一つだけはアピールしておきたいところが何なのか、はっきりさせてから臨んだほうが良かったと終わってから後悔した。“かみきょく”しか印象に残ってなかったらどうしよう……
この日に読んでいたのは北川眞也『アンチ・ジオポリティクス』。後々、三次面接で役立った。
二次面接
2024年4月24日(水)
「小説とかも書くの?」「はい」「内省的なやつ?」とのやりとりがあり、内省人間ことわたしはにじみ出る内省の香りを必死で抑えようとしたが無駄だった。そんなわたしに差し向けられたつぎの質問。「『東京都同情塔』の“批評”をしてください」。内省が得意な人間は批評も得意そうに見えたのか、というのはもちろん冗談だが(ESに批評への言及もあった)、しどろもどろになりつつ答える。全面接で一番肝が冷えた瞬間だった。
この日に読みかえしたのは町屋良平『生きる演技』。余談だが、後日5月7日に池袋ジュンク堂で行われたイベントに足を運んだら、面接をしてくださった方がまさに『東京都同情塔』の編集者であったことを知り、勝手な“批評”をしてしまったわたしは再度内省の底に沈むことになった。
三次面接
2024年5月8日(水)
友人と作ろうとしていたインディーゲームで、就活をテーマにしたものがあった。簡単に言うと、“ガクチカカード”なるものを使ってイジワル面接官をうち負かす、というPCゲームなのだが、そのカードは学生生活のパートで集めなければならない。大学1〜3年生の行動ターンで集めたカードが、面接バトルで使用可能になるわけだ。たとえば強力なガクチカカード「イベントサークルの幹事長」を作ろうとした場合、「GPA0.1」というデメリットカードを引いてしまう可能性もある。
しかしながら、この「ガクチカ」なるものがほとんど問われていない、と気付いたのはだいたいこの面接からだったように思う。ついでに言うと、イジワル面接官もいない。問われたのは、あらゆる事象に関して普段から考えていること、その瞬発力や蓄積ではなかったかと思う。『新潮』の他の文芸誌との違いや、『文藝春秋』などの総合誌の役割などから、ガザ、ウクライナの戦争、そして移民問題まで、未整形の考えを言葉にかたどっていく。それは決まった形をもった「カード」などではありえないだろう。沈黙し、考えている間でも答えを待ってくれたのがとても嬉しかった。
この日に読んでいたのは荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』。
最終面接
2024年5月13日(月)
面接の受け答えでうまくいったことなどなく、いつも終わってからこれを言えばよかった、あれは言わなければよかった、と後悔するのだった。用意してきた言葉は話しているうちにずれを感じて、弱い斜面から崩れていく。その上に重ねる言葉は空を切り、いつもあとになってから、空白にピッタリと嵌る適切な言葉がなんだったのかわかってくる。待合室、わたしの背後にあったのは十万部を超えた書籍の並ぶ書棚だった。その中には、かなり古いものから新しいものまで、愛読してきた本が無数にあった。ここにある小説が時代を超えて読みつがれるのは、フィクションが現実に対して取りもつ「遅れ」をある意味で引き受けつつ書かれているからなのではないかと思う。「遅れ」を引き受けつつ、「遅れ」が「早さ」に転化する地点を探ること。つまるところそれは、これまでに誰かが書き、話してきた言葉の集積である「わたしの言葉」の遅れを、あせらずに、崩れともども信じつづけることなのかもしれない。そんなことを考えながら、面接室に足を踏み入れた。
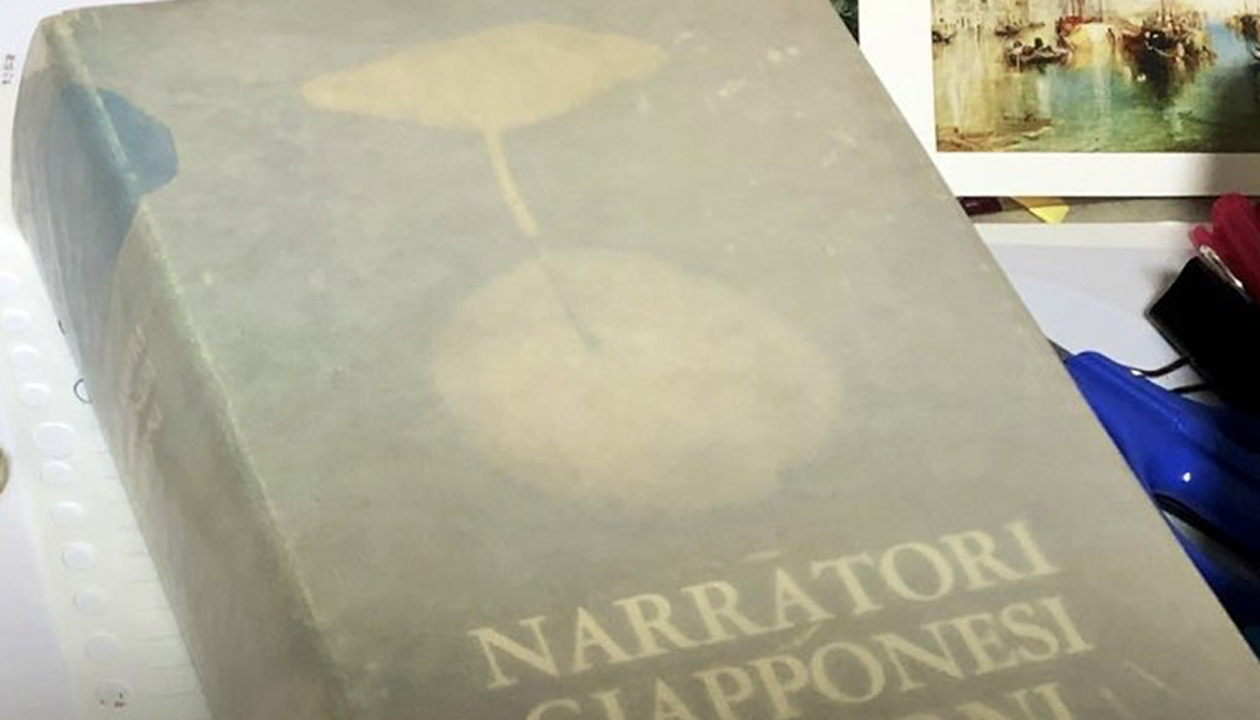
① 須賀敦子がイタリア語に翻訳した日本文学選集。外国語の本を読んでいると時間を忘れられるため、最終面接が終わり、合否の電話がかかってくる間に読んでいました。

最終面接の前日は山に登っていました。
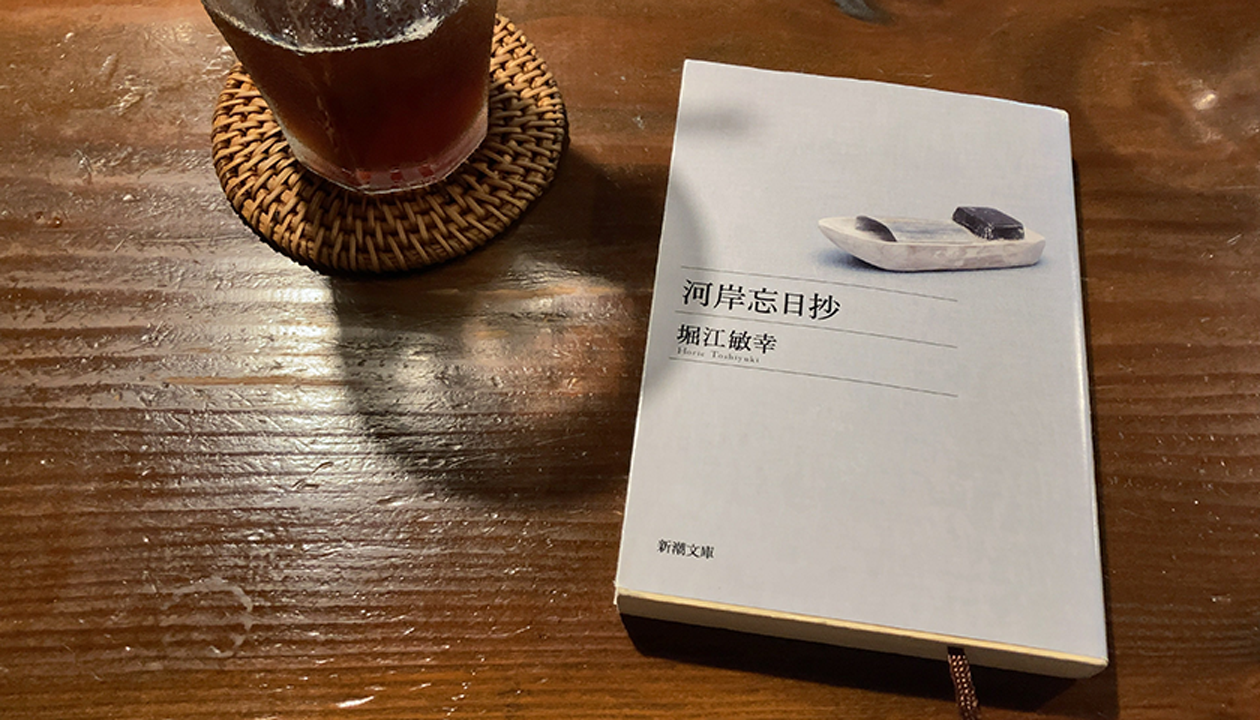
面接の後には喫茶店で本を読み、その日のことを考えないようにしていました。

