営業部 社員インタビュー
I・Kさん
2020年入社。
2020年より営業部。
仕事の紹介

パネルやPOP入り紙袋を携えて、いざ書店回り。
営業部の仕事は大きくわけて二つ。一つは、自分が担当している本の販売施策の企画。私の場合だと文庫と文芸の単行本です。ここには文庫のフェアや、作家の周年企画なども含まれます。
営業としての立場で、データ分析や書店営業活動から得た知見を活かし、表紙や帯のコピーの方向性、宣伝物案について編集部に提案します。
この仕事で重要なのは、読者を理解することです。とりわけ、本は相当に幅広い趣味嗜好に開かれていますから、自分にとって身近ではない領域についても、好きなジャンルでも、バイアスを取り払い、根拠に基づいて読者を理解することが必要です。
その為に、常にあらゆるジャンルの本の、読者の年齢構成や性別、一緒に読んでいる本といったデータから多角的に分析しています。
同じ著者やジャンルの本でも、装幀やコピーでアピールする要素が異なれば読者の傾向は大きく変わります。どういった読者に届けるか、という狙いの解像度を可能な限り上げることが、売り伸ばしの成否に関わると考えています。
また、他社の事例研究をすることもしばしばあります。装幀やコピーだけでなく、情報解禁の段取り、パブリシティでの取り上げられ方やその宣伝物への活用等、自社の本に応用出来るケースがないか常に意識しています。
営業は、本を一から作る編集者とは異なり、よりよい企画になるよう判断材料を提供することが役割だと考えています。その本のポテンシャルが十二分に発揮され、より多くの潜在的な読者に届くよう力を尽くす、という姿勢で臨んでいます。
もう一つが、書店営業で、担当している書店へ新潮社の本を売り込み、より大きく展開していただいて売上を最大化することが目的になります。
ただ、本は買い切りではなく委託販売なので、沢山本を注文してもらって終わり、というわけではありません。そこで、本がより売れるよう、企画の狙いが最大限発揮されるような売り場作りをしていただくことが最も重要になります。
そこで大事なのが、日々の営業活動の中で積み重ねてきた書店員さんとの信頼関係です。
書店員さんはやはり本好きが多いので、お互いの、作家や装幀の個人的な好みの話だとか、最近読んで面白かった本の話に脱線することも度々あります。そうした雑談から施策のヒントが見つかることも。
つまるところ、新潮社の本の魅力を、いかにそのお店に最適な形で売り場に落とし込んで、ベストな状態で読者の方々に届けてもらうか、というところだと思います。
入社後一番の思い出
営業担当として、ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』を担当したことです。海外文学に関心のない人、更には、普段小説を読まない人に如何にこの世界的名作を手に取ってもらうかという視点を軸に戦略を入念に練りました。まず、「どのような形で話題になるとよいか」のゴールを設定し、そこから逆算して情報解禁のスケジュールや宣伝物の文言を検討していきました。
リリースでは「ラテンアメリカ文学」「マジックリアリズム」のような文学的な説明はあえて避け、「文庫化の実現は世界が終わる時」という都市伝説の紹介から、文庫の装画者がNHK朝ドラ『虎に翼』のメインビジュアルを手がけた人であることなど、親しみやすく間口を広げていきました。元々自分自身は海外文学が好きなので、新しい読者には、とにかく肩の力を抜いてフラットな気持ちで物語に没入して欲しい、という個人的な熱意が原動力にもなりました。
結果は皆さんもご存じの通りの大反響で、10月現在、10回重版をし34万部を突破。もちろん営業部員としても嬉しいですが、なにより、一人の本好きとしてとても感慨深かったです。
ある日のスケジュール
- 7:00
- 起床。行きの電車ではボーッとしています。
- 9:00
- 出社。出版業界関連のニュースをまとめてチェック。
他の版元の取り組み等から学べるところがないか常に目を配っています。その後、溜まっているメールに対応。
- 9:30
- 担当している新刊の売行きをチェック。
重版が出来そうな本はデータを揃え上司と検討します。緊張の瞬間。
無事重版が決まったら書店への案内を作成します。
- 11:00
- 往年のロングセラーの売上が突如として急増!
原因をエゴサーチすると、SNSでの紹介でバズっていたことが判明。
ヒットの種は今やどこにでも転がっています。
帯や宣伝物等にその人の推薦コメントが使えないか他部署と検討。スピードが重要です。
- 13:00
- 新潮文庫nexの月例会議に出席。
新刊のタイトル案やカバーの方向性、販売戦略について、編集、プロモーション、装幀の担当者と議論を重ねます。
- 16:00
- 半年後に刊行予定になっている大型新刊の打合せの準備。
モデルケースとなりそうな既刊本の販売戦略の分析や、情報解禁のスケジュール、SNSとの連携、
どういった要素をアピールするべきか、などたたき台をつくっておきます。
- 17:00
- 担当の書店へ訪問し、目玉新刊を紹介。本の趣味が合う方で話が横道に逸れることもしばしば。
ついでに気になっていた他社の新刊を購入。売り場を巡回して、他社の本の宣伝物等もチェックしています。
- 20:00
- 直帰。夕飯は自炊が多いです。料理をしている時間は仕事の息抜きになっているなぁ、と感じています。
その後は映画を観たり、本を読んだりしています。
- 24:00
- 就寝。
Off-Time
大学の映画サークル時代の友人らとキャンプ。この日はパエリア、ローストチキンにおでんという謎ラインナップ。しこたま食べてしこたま飲みました。普段はどうしても仕事の事ばかり考えてしまうので、オフは全然関係ないことをするのがいいかな、と思っています。

もちろん翌日は二日酔い。
わたしの「人生の一冊」(新潮社刊)
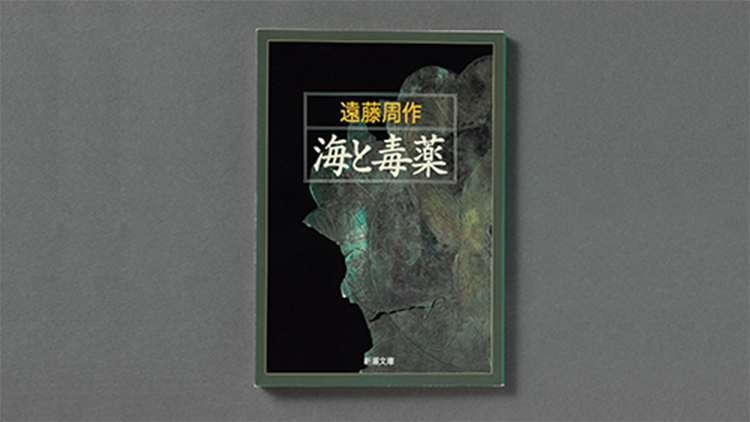
『海と毒薬』(遠藤周作)
中学生の時、試験問題で『海と毒薬』の一節を読み、衝撃を受けました。塾帰りにその足で書店に駆け込み一気読み。未知の感情との出会いも本の魅力だと知った、忘れられない記憶です。
就職活動中の皆さんへ
新潮社で働く前、2年間別の業界で働いていました。初めての就活の時は、深いことは考えず、自分が好きなものを扱っている会社を受けました。出版社だけでなく、映画やラジオ、嗜好品業界等……。結果はあまり芳しくなく、愕然としましたが、今思い返すと敗因は明らか。好きだという漠然とした気持ちだけ先走りして、どのような形で関わっていきたいかクリアになっていなかったからです。どういうきっかけで好きになり、どういうところが好きなのか。そうした、自分の「好き」を様々な角度から掘り下げることが必要だと思います。
また、面接のアドバイスですが、面接官との会話を楽しんでください。自分の「好き」に自信さえあれば、あとはその表し方が大切です。品行方正に振る舞え、という意味ではありません。相手との共通項を探りながら、深く響く言葉を模索する。就活だからって自分を変える必要なんてないと思えば、リラックスして臨めると思います。

